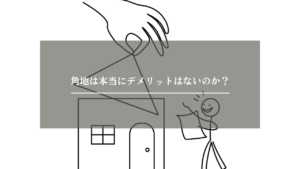戸建てとマンションどっちが正解?30年総額で見ると?
「そろそろ家を買いたい。でも戸建てとマンション、どっちにすればいいか決められない…」
こんなふうに迷っていませんか?
価格だけを比べて決めてしまうと、あとから「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうことも。
そこでこの記事では、30年先まで見据えたお金の比較、暮らしやすさ、立地や管理の現実まで、家づくりのプロとしてわかりやすく解説します。
30年総額で見る!戸建てとマンションのコスト比較

以下はあくまでモデル例ですが、「戸建て」または「マンション」を比較する際に見るべき項目をすべて入れた30年総額比較表です。このような表を実際の数値で埋めていくことで、「どちらが得か」を比較できます。
「マンションは管理費や修繕積立金がかかる」とは聞いたことがあるかもしれません。
でも、実際に30年分の総額にするとどれくらい差が出るかご存じですか?
| 費用項目 | マンション(モデル例) | 戸建て(モデル例) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 3,500万円+諸費用 | 3,200万円+諸費用 |
| ローン利息累計 | 約600万円 | 約550万円 |
| 固定資産税・保険 | 約300万円 | 約330万円 |
| 管理費+修繕積立金 | 約1,000万円 | ― |
| 駐車場代 | 約360万円 | 敷地内無料 |
| 外壁・屋根・設備修繕 | ― | 約400万円 |
| 30年総額 | 約5,760万円 | 約4,480万円 |
※地域や物件条件によって変動しますが、管理費・駐車場代が積み重なるマンションは、30年で1,000万円以上の差になることもあります。
売却時にどうなるか?残債と資産価値もチェック
30年後、あなたの家はどれくらいの価値が残るでしょうか?
戸建てorマンション
- 戸建て:建物の価値は下がるものの、土地の価値は残る
- マンション:建物と土地を合わせた価値は築年数で下がり、場合によっては売却価格がローン残債を下回ることも
資産価値を重視するなら、立地の良さや再販性の高い物件かどうかを確認しておくと安心です。
売却 / 賃貸化シナリオで見る資産性
お金の比較は、単に支出を比べるだけでなく“出口(売却・賃貸)”を含めて考えることが重要です。
残債 vs 想定売却価格(10年・20年・30年想定)
家を買うときは、**出口戦略(売却・賃貸)**も考えておくと安心です。
下の表は、同じ購入価格(3,500万円)・同じ条件でローンを組んだ場合の、10年・20年・30年時点の「残債」と「想定売却価格」を比較したイメージです。
| 年数 | 戸建て:残債 | 戸建て:想定売却価格 | 差額 | マンション:残債 | マンション:想定売却価格 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年後 | 約2,500万円 | 約3,000万円(土地価値+建物残存) | +500万円 | 約2,500万円 | 約2,800万円 | +300万円 |
| 20年後 | 約1,400万円 | 約2,500万円(土地価値中心) | +1,100万円 | 約1,400万円 | 約2,000万円 | +600万円 |
| 30年後 | 約0円 | 約2,300万円(土地価値ほぼのみ) | +2,300万円 | 約0円 | 約1,600万円 | +1,600万円 |
※想定価格は地域や市況により大きく変動します。ここでは戸建ては土地価値が残る前提、マンションは築30年で建物価値が大きく減少する前提で試算しています。
表から読み取れるポイント!
- 戸建ては土地価値が資産として残りやすいため、30年後も売却益が残る可能性が高い
- マンションも駅近や人気エリアなら価格下落は緩やかですが、築年数による価値減少は避けられない
- 10〜20年で住み替えを考えるなら、どちらも「売却価格 − 残債」がプラスかどうか確認しておくと安心
たとえば、あるモデルでは、戸建ては土地価値を残すため損失が限定的になるケース、一方マンションは建物部分の劣化が資産価値を抑えるケースもあります。
目安事例(よくある3ケース)
以下は、よくあるパターンを想定した“目安”としての簡易事例です。
| ケース | 想定条件 | 戸建ての場合の30年総額目安 | マンションの場合の30年総額目安 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| A:郊外・ファミリー | 駅徒歩15分、庭付、車2台 | 約4,200万円 | 約5,000万円 | メンテナンスを計画的に行えば戸建てが有利 |
| B:都心近く・共働き | 駅徒歩5分、階数高め | 約5,500万円 | 約5,600万円 | 利便性を取ればマンションと拮抗する可能性あり |
| C:セカンドライフ | 小規模住居、駅近 | 約3,200万円 | 約3,500万円 | メンテナンス負荷を軽くしたマンションも選択肢になり得る |
(これらはあくまで目安。実際は土地価格、建物仕様、地域性で大きく変わります。)
上記を踏まえると、たいていのケースで戸建ての方がランニングコストを抑えやすい傾向がありますが、利便性が高く、売却・賃貸性が強いマンションも選択肢としてありです。
もし、ご自身の希望エリア・土地価格・ローン条件で「あなたの場合はどうなるか?」を見てみたい方は、無料試算を私たちにプロにご相談ください。
ライフイベント別に戸建て・マンションを比較!あなたに合うのはどっち?

住宅を選ぶ際、「子育て」「共働き」「ペット」「老後」などライフステージの変化を見越しておくことが非常に大切です。ただし、人によって重視するポイントは異なります。
ここでは、各ステージで「戸建て/マンションどっちが向くか」の判断材料を提供します。
ライフイベント別チェックリスト:戸建てかマンションかを判断するには?
まずは、あなた自身が「重視したいこと」を可視化するためのチェックリストです。これを元に「戸建て寄り/マンション寄り」の傾向を見ていきます。
戸建て/マンションどっちが有利?
| 重視すること | 戸建てが有利なポイント | マンションが有利なポイント |
|---|---|---|
| 防音・音ストレス | 隣接距離が少なく、音の干渉を抑えやすい | 構造・遮音設計がしっかりしたマンションなら音対策されていることも |
| ベビーカー・動線の快適さ | 段差やスロープを自由に設計できる | 共用通路・エントランスの段差や扉幅を確認すれば許容範囲もあり得る |
| 在宅ワーク・静かな仕事場 | 間取り変更や遮音壁を自由に入れられる | 上下・左右の騒音を避ける部屋配置や窓向きで対応可能 |
| 将来のバリアフリー対応 | 段差のない設計、手すり設置、動線変更がしやすい | エレベーター付きマンションなら移動負荷が軽くなるが停電時リスクを確認 |
| ペット飼育 | 規約制限なし、自宅の外構や庭で自由対応可能 | 規約で飼育条件が定められていることが多いが、ペット可物件を選ぶことで対応可能 |
| 間取り自由度・改修可能性 | 構造制限が少ないため、将来の増改築や間取り変更がしやすい | 規約・構造制限があるため、大幅な間取り変更は厳しい場合がある |
このチェック表の各重視点について、実際に住むときに意識すべきことを、ライフステージ別に解説します。
子育て期で重視すべきこと
共働き × 在宅勤務期で意識すべきこと
ペットを飼いたい人向けチェックポイント
シニア期・老後を見据えた視点
子育て期で重視すべきこと
動線のスムーズさと段差対策
赤ちゃんを抱えて移動することが多いこの時期、段差・スロープ・扉幅はストレス源になります。
戸建てならこれらを最初から最適化できます。マンションでは、エントランスから玄関までの段差や廊下幅、スロープ有無を必ず確認してください。
また、リビング・キッチン・洗面・お風呂の距離感も“子育て動線”として重要です。
騒音・隣住戸音への配慮
子どもの跳びはねや走り回る音は、上下左右に伝わりやすいため、遮音性能が鍵です。
マンションを選ぶなら、床材・天井裏の防音仕様を確認しましょう。戸建てなら敷地配置(隣家との距離、植栽や塀の配置)で騒音抑制が可能です。
(例:あるママが「マンションで子どもの足音を気にするようになった」とブログで綴っていました)
間取り配置・部屋の使い勝手
「長い廊下」「リビングから遠い洗面・浴室」などは、子育て期では不便と感じられることがあります。特に洗濯・家事に追われる日々では、動線効率が暮らしの満足度を左右します。
新築マンション購入者が、「買ってから気づいた子育てに合わない間取り」の失敗例を挙げています。
共働き × 在宅勤務期で意識すべきこと
静かな仕事空間の確保
仕事に集中したい時間帯に、家族の生活音(キッチン、子どもの声、テレビなど)と干渉しない部屋配置が理想です。
戸建てでは、書斎を隣家と離した場所にする設計が可能です。マンションでは、反対側の部屋・角住戸・窓の向きがカギになるでしょう。
インフラ・通信環境と配線設計
高速インターネットや有線LAN、電源配線などをあらかじめ設計できる戸建ては有利です。
マンションでは配線ルートや共用設備の制限があることもあるので、購入前にネット設備導入可否を確認しておきましょう。
宅配・荷物対応の利便性
共働きの場合、荷物の受け取りが負担になりがちです。戸建てなら門扉内に宅配BOX設置ができます。
マンションでは共用玄関や宅配ロッカー設置がされている物件を選ぶと安心です。
ペットを飼いたい人向けチェックポイント
規約制限と許可条件
多くのマンションでは「犬・猫の飼育可否・頭数制限・体重制限」などの規約があります。購入前に規約全文を確認しておきましょう。
戸建てでは法的制限は少ないですが、騒音や糞尿などの近隣配慮が常につきまといます。
外構・庭・散歩導線
戸建てなら庭や敷地で自由にペットスペースを設計できます。
マンションでは共用通路や敷地外を通る散歩導線、足洗い場など工夫が必要になります。
シニア期・老後を見据えた視点
段差レス・バリアフリー設計
将来階段の昇降が困難になる可能性を考えて、平屋風設計・スロープ設計・手すり設置などを初期段階で設計できる戸建ては安心感があります。
マンションでは、入口〜住戸間の段差、廊下幅、エレベーター利用可能性を必ず確認しましょう。
将来の移動負荷と災害時リスク
高層階住戸では、地震や停電時のエレベーター停止が懸念されます。
□ 非常階段の幅、段数、誘導灯設備
□ 停電時エレベーター復旧見込み
□ 階段を日常的に使う負荷(健康状態との兼ね合い)
これらをチェックするリストも用意しておくと安心です。
規約でできないことリスト(マンション制約例)
実際にマンションでは規約・条例で次のような制約が設けられていることがあります。
これらは、管理組合規約や都市条例によって定められており、購入前に必ず目を通すべき部分です。違反すると許可が下りない、または将来売却時にトラブルになることもあります。
実在の体験談紹介
ここでは、実際にマンション/戸建て選択で悩んだ方の体験談をご紹介します(出典記載)。
✔️ 戸建てを選んで良かったという声
戸建てを選択した方の体験談1
子育て家族が都内マンションから郊外戸建てに住み替えたこちらの方は、静かな暮らし・家族時間が増えたが、光熱費や維持コストの負担も感じるという本音が語られています。
参照:つぃはなのイエタテブログ
戸建てを選択した方の体験談2
30代でマンションを選んだこちらの方は「買ってみて初めて気づいた生活音・間取りの違和感」などリアルな悩みが綴られています。
参照:どんどん育児
✔️ マンションを選んで良かったという声
マンションを選択した方の体験談1
この方は、マンションを購入して 「住環境としての安心感」 と 「資産性の可能性」 の両面で満足していると語っています。特に、「“自分の家”を持っている安心」が精神的な価値になっている、との感想が印象的です。
参照:NOTE
マンションを選択した方の体験談2
テレワークやペットとの生活を考えて選ばれたという記事で、通勤利便性・共用設備・快適性のバランスが評価されています。
参照:SUMAU
これらの体験談を読むと、理想と現実のギャップや「何を妥協できるか/できないか」が、選択の鍵になることが感じられます。
立地と管理の現実を比較!マンションか戸建てか

「駅近マンションがいいのか?郊外戸建てがいいのか?」
この悩みは、多くの方が最後まで決めきれないポイントです。
ここでは、立地の優先度 × 建物タイプの組み合わせをわかりやすく比較してみましょう。
立地優先度 × 建物タイプ
各パターンのメリット/トレードオフを整理すると読者にとって理解しやすくなります。
立地優先度 × 建物タイプマトリクス
| 立地/建物タイプ | 駅徒歩5分以内 | 駅徒歩10〜15分 | 郊外(車前提) |
|---|---|---|---|
| マンション | ✅ 価格高めだが資産価値が落ちにくい ✅ 通勤・通学が快適 ⚠️ 騒音・人通りが多い | ✅ 価格と利便性のバランスが良い ✅ 駐車場代が抑えられる物件もあり ⚠️ 将来の値上がりリスクあり | ✅ 専有面積が広めで快適 ⚠️ 通勤・買物に時間とコストがかかる |
| 戸建て | ✅ 狭小でも土地価値は残りやすい ⚠️ 土地価格が高く庭が取れないことも | ✅ コストと広さのバランスが良い ✅ 車と公共交通を使い分け可能 | ✅ 庭・駐車場・収納スペースが充実 ⚠️ 車必須でガソリン代・維持費が増える |
月間移動コストで比較
立地選びでは「毎月の移動コスト」も意外と大きな差になります。
以下のように、定期代・ガソリン代・駐輪代・駐車場代を合算して家計に組み込みましょう。
| 項目 | 駅近マンション | 郊外戸建て |
|---|---|---|
| 定期代 | 約20,000円 | 約30,000円 |
| ガソリン代 | 0〜5,000円 | 約25,000円 |
| 駐輪・駐車場 | 約10,000円(機械式駐車場含む) | 敷地内0円 |
| 合計 | 約30,000円前後 | 約55,000円前後 |
車2台持ちになるとガソリン代・保険代・車検代が倍増するため、郊外戸建てのコストはさらに増えます。「毎月の移動費 × 12か月 × 30年」で試算すると、立地の選び方がいかに総コストに響くかがわかります。
ハザード・防災チェックの手順ガイド
災害リスクを見落とすと、いざというときに大変です。以下のステップで調べましょう。
- 1.国土地理院のハザードマップにアクセス
- → ハザードマップポータルサイトへアクセス!スマホ・PCどちらでも利用可能。PCのほうが範囲を広く見られるのでおすすめです。
- 2.画面左上の検索窓に住所を入力し、洪水・土砂災害・津波リスクを確認
- 検索バーに「市区町村+番地」を入力するとピンが立ちます。
画面右側のメニューで「洪水」「土砂災害」「高潮」「津波」など見たい災害種別を選択できます。
- 3.浸水深の色分けをチェック(0.5m未満〜3m以上など)
- 0.5m未満 → 床下浸水レベル
0.5〜3.0m → 床上浸水レベル(家の中まで水が来る可能性)
3m以上 → 2階まで浸水する可能性があるエリア
目安として、0.5〜3.0m以上のエリアは避けるか、床高を上げる設計が必要です。
- 4.地盤の強さ(液状化リスク)や標高も確認
- 国土地理院「土地条件図」や自治体サイトで地盤情報を確認可能。
埋立地や軟弱地盤のエリアは液状化リスクが高い傾向があります。
- 5.最寄りの避難所を表示し、徒歩ルートを実際に歩いて確かめる
- 徒歩何分かかるか実際に歩いてみる
夜間や雨の日も想定して安全性をチェック
避難所の収容人数やペット同伴可否も調べておくと安心
候補地が複数ある場合は、同じ手順で比較すると「どの土地が安全か」が明確になります。また候補地AとBで浸水深・避難所距離を並べて比較すると、どちらが安全か一目でわかります。
*自治体独自のハザード情報(避難所運営マニュアル、防災倉庫位置など)が載っている場合があります。実際に、過去の冠水履歴や、実際に避難した経験談を聞くとリアルなリスクを知ることができます。
高層マンションのエレベーター停止時チェックリスト
マンションを選ぶ場合は、災害時にエレベーターが止まったときの生活を想像してみてください。
□ 非常階段の段数と幅を確認(荷物を持って昇降できるか?)
□ 給水設備の非常用ポンプ有無を確認
□ 停電時にトイレが使えるかどうか確認
□ 管理組合が災害時対応マニュアルを持っているか確認
実際にエレベーターが停止した際、復旧まで数日かかるケースも報告されています。非常用備蓄・水・簡易トイレを準備しておくと安心です。
管理の手間・コストを比較
| 項目 | マンション | 戸建て |
|---|---|---|
| 共用部清掃 | 管理会社が実施(管理費に含まれる) | 自分で掃除 or 外注 |
| 修繕計画 | 管理組合で計画的に実施 | 自分でタイミングを決定 |
| 町内会・近隣付き合い | ルールが明確で負担少なめ | ご近所付き合いが密になることも |
| ゴミ出し | 集積場や24時間ゴミ出し可能な物件も | 指定日・指定時間に自分で出す |
未来を見据えた選び方「私の場合はどっち?」
どちらが正解かは人によって違います。
最後に、どんな人が戸建て向きか/マンション向きかをまとめました。あなたのライフスタイルに当てはめて考えてみましょう。
🏡 戸建てが向いている人
- 子どもをのびのび育てたい人
足音や騒音をあまり気にせず、庭や駐車場で自由に遊ばせたい人に向いています。 - DIYや家のカスタマイズが好きな人
間取り変更や外構リフォーム、太陽光パネル設置など、自由に手を入れたい人に最適です。 - ペットと暮らしたい人
頭数や大きさの制限なく飼えるので、多頭飼いを考えている家庭にも向きます。 - 土地を資産として残したい人
将来売却や相続を考える際、土地の価値が残るのは大きなメリットです。
🏢 マンションが向いている人
- 駅近・都心の利便性を重視する人
通勤時間を短縮し、買い物や病院など生活施設が近い環境で暮らしたい人にぴったりです。 - セキュリティや管理体制を重視する人
オートロックや管理人常駐、共用部の清掃や修繕を任せたい人におすすめです。 - 共働き・外出が多い人
ゴミ出し24時間可、宅配ボックスなど、日常の手間を減らす仕組みが揃っています。 - 将来の売却や賃貸化を見据える人
駅近・人気エリアなら資産価値が落ちにくく、住み替えや賃貸運用も比較的しやすいです。
⚖️ 両方検討すべき人
- 立地と広さのバランスで迷っている人
郊外マンションや駅徒歩圏の小さめ戸建てなど「中間選択肢」も検討すると良いでしょう。 - ライフステージが変わりそうな人
結婚、出産、親との同居、転勤などが見込まれる場合は、将来の売却しやすさや間取り変更のしやすさを重視すると安心です。 - 老後の暮らし方がまだ定まっていない人
バリアフリー改修や階段の有無、エレベーターの有無などを考慮し、将来も快適に住める選択肢を比較しましょう。
どちらを選んでも、大事なのは「未来の暮らしを具体的にイメージすること」です。
30年先のライフスタイル・家計・家族構成を想像して、総コストや利便性と照らし合わせて選びましょう。
まとめ:戸建てかマンションか?決断前に知っておきたいこと
ここまでご紹介してきた内容を整理すると、戸建てかマンションかを選ぶ際には主に次の3視点で比較すべきです。
- 30年総額・維持コスト
管理費・修繕積立金・駐車場代などを含めると、マンションのランニングコストは戸建てより高くなりやすい傾向があります(例:30年で差500万円前後という試算もあります) - 暮らしの自由度・将来変化対応力
ライフステージ変化(子育て・在宅勤務・老後)を前提に、動線・規約制限・間取り変更余地などを重視すべきです。 - 立地・交通・管理の現実性
駅近かどうか、坂道・坂道動線、災害リスク、管理手間、共用部運用などを含めた実用性を比べることが不可欠です。
もし、今あなたが
- 通勤利便を最優先したいなら → 駅近マンションが優勢
- 広さ・庭・カスタマイズ性を望むなら → 郊外戸建てが強み
- 将来の売却性を考慮するなら → 立地条件を重視して選ぶ
というような仮説を立て、実際の土地・物件を当てはめて比較試算してみることをおすすめします。

もしよろしければ、あなたの希望エリア/土地価格/必要広さをお聞きして、あすなろ建築工房で無料試算・比較表づくりをお手伝いできます。ご希望でしたらお気軽にお知らせください。⇒無料試算を私たちにプロのあすなろ建築工房にご相談ください
他の記事をみる