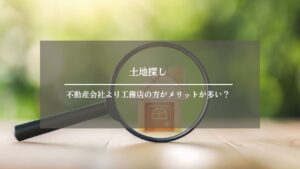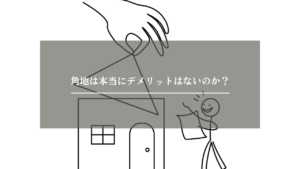気密性能を表すC値とは?窓でこんなに暮らしが変わるって本当?
「施工する住宅の平均C値はいくつですか?」
「C値を0.5以下に出来ますか?」
といったご質問を頂くことが時折あります。
これまで一般のお客さまにはあまり知られていなかった「C値」ですが、最近ではYouTubeなどの影響もあり、関心を持たれる方が増えてきました。具体的に興味を持たれるケースも多くなっています。
そこで今回は「快適に住まうために必要な気密性能」についての解説をしていきます。
C値とは?気密性能を表す重要な指標の意味と求め方

C値とは「相当隙間面積」という単位です。
| 建物全体の外皮にある隙間の面積(㎠)の合計を延床面積(㎡)で割った数値を指し、単位は、「㎠/㎡」になります。 |
簡単に言うと、30坪の床面積つまりは100㎡のお家の場合、C値が1.0となると、家の隙間を集めると100㎠あるということになります。
100㎠というと10cm×10cmの穴なので、なかなか大きいですね。
ちなみにC値は少数第一位で示されます。
隙間の面積を延床面積で割った数字の小数第2位を4捨5入して、小数点以下1桁で表すのが正解です。
よって、C値0.35という数値となった場合、それはC値0.4の性能として表記するのが正となります。
第一位までしか求めないということは、つまりは「小数点第2位以下は、大した差ではない」ということを覚えておいてください。
C値は小さい方がいいのか?目安と注意点を解説
最近、一部の間で「C値の競争」が起こっているように感じます。
もちろんC値は、小さければ小さいほど換気計画を正しく出来るようになるので、C値は小さければ小さいほどよいのは確か。
C値が小さいこと自体に問題があるわけではありませんが、その数値をより小さくしようとすることで、かえって別の課題が生まれてしまう場合もあるということは、知っておいて損はないかもしれません。
気密性能に大きく影響するのは窓だった!C値を左右する原因とは
正しく高気密高断熱の基本を理解している方の中には、「ある一定以上のC値を過度に追い求めることには、それほど意味がない」と考える方も少なくありません。
実は、気密を気にして施工することが当然になると、壁からの漏気はほとんどなくなり、気密の数値を上げる原因箇所のほとんどが「窓」になります。
外壁のパネルの目地や窓周りや設備配管の貫通部には、かなり意識して気密処理をしています。ここまで来ると、C値を左右するのは、ほとんどが窓の気密性能です。
C値を「0.5以下」とか「0.3以下」とするのは可能ですが、そのためには窓自体の気密性能が高い窓を採用する必要がでてきます。
リビングやダイニングからウッドデッキにつながる窓や、南面に面した子ども室や主寝室の窓は、日射取得を多く得るために「引き違い窓」とする場合が多いです。
「引き違い窓」は大きな開口部が得られ、外部との連続性を得るのに有効な窓です。ですが、気密性能が比較的低くなるという弱点があります。
「引き違い窓」が1つあるだけで、その家のC値が0.1変わることもあります。
この引き違い窓が一番の気密のポイントとなる部分なのです。
C値を下げるにはどんな窓を選ぶべき?気密性が高い窓の選び方

家全体の気密性能を高めるには、この気密性能の確保が難しいとされる「引き違い窓」を避け、より気密性能に優れた「開き窓」や「引き寄せ機能の付きの窓」などを選ぶ工夫が有効です。
しかし、せっかくダイニングと連続するウッドデッキを設けても、空間をつなぐ窓が「出入りしにくい」閉鎖的な窓では、ウッドデッキの存在価値も半減してしまいます。
「開き窓」にすると、中間期で通風を確保したい時に開け放しするのが不便だったり、網戸が付けにくかったり、ウッドデッキとの一体感が損なわれてしまったりします。
C値を小さくするために、普段使いの窓が「使いにくい窓」になるのは避けたいですよね。
そこで開放的かつ性能を確保するために「引き寄せ機能のある窓」が有効な手段です。
「引き寄せ機能のある窓」は、一般的な「引き違い窓」と比べると、建設費用全体での窓にかかるコスト比重が大きくなります。
C値を0.3以下にすべき?パッシブハウス認定の基準と必要条件
C値を意識的に小さくしなくてはいけない場合もあります。
ドイツの基準であるパッシブハウス認定をうけるためには、この気密に関して細かな基準が設けられています。
- 冷暖房負荷が 各15kWh/㎡以下である
- 気密性能として50Paの加圧時の漏気回数が0.6回以下である
- 一次エネルギー消費量(家電も含む)が120kWh/㎡以下である
この3つをクリアする必要があります。
断熱材を厚くして性能の良い窓を採用し、高効率の換気装置を導入すると、冷暖房負荷の基準と一時エネルギー消費量の基準はなんとかクリアすることが可能です。
通常より断熱材を厚くし、高性能なガラスとサッシを採用し、高効率な換気装置を採用する必要があるのです。
漏気回数の基準は、実際の現場での測定によって確認されるため、設計上の数値だけでなく、施工の丁寧さがともなってはじめてクリアできるものです。
パッシブハウス認定基準である「50Paの加圧時の漏気回数が0.6回」という気密性能は、C値でいうと0.2c㎡/㎡程度となります。
そのため、余裕を持って「C値0.1クリア」を目指す必要があるのです。
実例紹介|C値0.1の施工事例と気密測定の工夫
事例①:いんたーハウス(伊勢原の家)
以前に竣工した「いんたーハウス(伊勢原の家)」はパッシブハウスの認定を受けています。
いんたーハウス(伊勢原の家)
気密シート施工後、大工工事終了時、完成時の3回気密測定を行いました。
工事段階でも、気密が確保されていることを確認しながら現場を進めています。
パッシブハウス認定を取得する際には基準を満たす必要があるので、確実な性能を確保するために3回の測定を行うようにしたのです。
通常は完成時に1回の測定で、全棟気密測定を行うようにしています。
ちなみに「いんたーハウス(伊勢原の家)」では、気密性能の確保のためにダイニングでは、引き寄せ機能のあるアルスさんの「エコスライド」という窓を採用しています。
ガラス面積が大きいため、ウッドデッキとの連続性も確保でき、気密性能も抜群です。


当社では「横浜でちょうどよい家」のコンセプトで家づくりを行っているため、公表するC値については「快適な住宅として必要とされるC値1.0以下」を社内基準としています。
一般的に引き違い窓を複数採用していることもあり、過度な数値競争とならないよう「C値1.0以下」とお伝えしていますが、実際の測定値はそれよりも小さい場合が多くなっています。
計測した結果、C値の測定値が0.5以下、0.3以下になることもあります。窓の形状にもよりますが、0.2~0.7が実測値となっています。
事例②:U-project ~築140年の古民家を住み継がれる家へ~
U-project ~築140年の古民家を住み継がれる家へ~
C値は設計内容によって結果や数値が変わるため、表向きの数値はあくまで「1.0以下」としています。
なお、床下エアコンを採用する場合には基礎断熱が必須となり、その場合は床下エアコンがしっかりと機能する数値として「0.6以下」を社内目標としています。
事例③:NOBBY HOUSE
たとえば、こちらの「NOBBY HOUSE」はC値「0.6」等級3を有しています。
NOBBY HOUSE
あくまで社内の目標であって、保証値とはしておりません。
第一種換気装置を設けるなど、換気の効率を求める場合には、気密性能が高い方が設計性能値を確保しやすくなります。
そのためC値0.6などの目標を定めることもありますが、C値を下げていくためには、性能の良い窓を多く採用する必要があり、コストアップにもつながります。さらに、C値が低い事例もあります。
事例④:WONDER HOUSE
WONDER HOUSEはC値0.4を実現しています。
WONDER HOUSE
気密性能はある程度(C値1.0以下)の性能を満たしていれば、生活するうえで不利益になることはありません。
逆に過当な気密性能を確保しようすると、利便性やコストメリットが崩れる結果にもつながる可能性があることをご認識いただければと思います。
築年数でC値はどれだけ変わる?経年劣化による気密性能の低下

木造住宅は、年月とともに木が痩せて少しずつ隙間ができたり、地震の揺れによって気密テープが傷むこともあります。
そうした自然の変化もあり、気密性能は少しずつ落ちていく傾向があります。
では、年数が経つとどれくらい気密性能が低下するのでしょうか。
やや古い記事ですが、竣工して15年経った家のC値を測定した結果を紹介している新聞(北海道住宅新聞)があります。
こちらを見ると、増築していたり、ストーブの穴をふさぐことが出来なかった事例を除いて、参考になる2軒のお家の隙間面積の低減率は22.8%と28.2%なっていました。約3割位低下する可能性があると見て良いでしょう。
コンセプトハウス兼自宅である「六ツ川の家」(建設当時のC値(相当隙間面積)は0.3)でも、経年変化を見るために気密測定した結果があります。
建設当時のC値(相当隙間面積)は0.3でしたが、0.4に変化しました。
経年変化により3割程度の性能低下が見られることからも、目安として新築時にC値が0.7を下回っていれば、長期的に見ても建物として十分な性能が保たれると考えられます。
まとめ
木造住宅は、建築後しばらくの間に木材が乾燥してやせていくため、徐々に隙間が生じることがあります。
また、耐震性能が十分でない住宅では、地震のたびに揺れによって構造に負担がかかり、その影響で気密性能も少しずつ低下していくことがあります。
どれほど高い気密性能を備えていても、耐震性が不十分な場合は、繰り返される揺れによって性能が損なわれてしまう可能性があるのです。
耐震性をしっかり確保して揺れにくい家にすること、そして木材の経年による変化で気密性能が3割ほど低下する可能性も見越して、あらかじめ十分な気密性を確保しておくことが大切です。
たとえば、将来的にもC値1.0以下を維持することを目指すなら、新築時にはC値0.7以下を目安にしておくと安心です。
家づくりをご検討されている方には、数値の追求そのものが目的になってしまわないように、費用対効果や将来の暮らしを見据えた、バランスのよい性能を備えた家づくりをしていただけたらと思います。
他の記事をみる