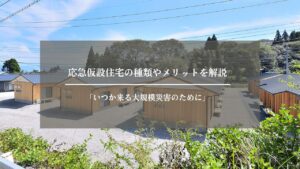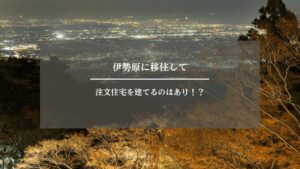老後はマンションが正解?維持費・バリアフリー・資産価値まで
老後の住まい選びは、人生後半を安心して過ごすための大きな決断です。
「マンションの管理費は年金で払えるのか?」
「介護やバリアフリーに対応できるのか?」
「資産価値は下がらないのか?」——。
この記事では、そんな不安に答えつつ、費用・住みやすさ・資産価値の3つの視点から老後マンションのリアルを徹底解説します。
老後にマンション購入・維持は本当に可能?費用と資金シミュレーション

老後にマンション暮らしを考えるとき、多くの方がまず不安を感じるのが「お金」です。退職金や年金でやっていけるのか、管理費や修繕積立金が払えなくなったらどうするのか、現実を見ていきましょう。
初期費用とランニングコストの現実
マンションにかかる費用は「買うとき」と「住み続けるとき」で大きく2種類あります。
| 項目 | 目安額(月額または一時金) | 補足 |
|---|---|---|
| 頭金・諸費用 | 300〜500万円 | 退職金の一部を充当する人が多い |
| 管理費 | 1.5〜2.5万円 | 共用部の規模や築年数で増減 |
| 修繕積立金 | 1〜2万円 | 築年数が進むと値上げが一般的 |
| 固定資産税 | 年10〜20万円 | 新築時は高め、築年数で減額傾向 |
| 駐車場代 | 月0.5〜2万円 | 車所有世帯に追加負担 |
📌 補足:国交省の調査によれば、修繕積立金は築30年で平均1.6倍に上がるケースが多いそうです。
つまり、老後資金計画は「値上げ前提」で立てることが必須です。
管理費・修繕積立金の推移イメージ 📈
築年数 平均管理費+修繕積立金(月額)
10年 約2.5万円
20年 約3.2万円
30年 約4.0万円
👉 築30年になると、毎月の支出が1.5倍以上に増える可能性が高いことをイメージしておきましょう。
老後資金モデルケース(キャッシュフロー例)
単身者(60歳・貯蓄3000万円・年金月15万円)
- 生活費:月15万円
- 住宅関連費:月5万円
- 年間収支:±0円
- 30年後:貯蓄3000万円は維持されるが、医療・介護費用次第で減少リスク
夫婦世帯(60歳・貯蓄2000万円・年金月22万円)
- 生活費:月20万円
- 住宅関連費:月5万円
- 年間収支:▲36万円
- 30年後:1000万円取り崩す必要あり
ポイント💡
- 医療費・介護費用の想定がカギ
シミュレーションでは生活費+住宅費をベースに計算していますが、実際には70代後半以降に医療費や介護費が大きく増える可能性があります。厚労省のデータによると、75歳以上の医療費は年間約90万円に達するケースもあり、これは貯蓄を大きく圧迫します。 - 修繕積立金の値上げリスク
築20年を超えると、修繕積立金は1.5倍〜2倍になるケースも珍しくありません。つまり「60歳の時点では月5万円で済んでいた住宅関連費が、80歳時点では月7〜8万円」に増える可能性があります。年表での収支赤字は、さらに拡大すると想定しておくべきです。 - インフレによる生活費増
食料品や光熱費の上昇が続けば、月20万円の生活費を想定しても実際は25万円必要になるかもしれません。特に電気代や水道代などの固定支出は削りづらく、家計を直撃します。 - 長寿リスク
平均寿命は延びており、女性では90歳を超える生活が珍しくなくなっています。「予定より長生きした場合、資金が尽きる」というリスクも忘れてはいけません。 - ライフイベントの変化
子どもの結婚支援や孫への教育費援助など、老後にも予想外の支出が発生します。マンション維持費だけでなく「家族イベントによる突発支出」も織り込んでおくと安心です。
年齢ごとの収支年表イメージ 📊
| 年齢 | 年金収入 | 支出(生活費+住宅費) | 年間収支 | 貯蓄残高 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 22万円 | 25万円 | ▲3万円 | 2000万円 |
| 70歳 | 22万円 | 26万円 | ▲4万円 | 1700万円 |
| 80歳 | 22万円 | 28万円 | ▲6万円 | 1300万円 |
| 90歳 | 22万円 | 30万円 | ▲8万円 | 800万円 |
👉 見えてくるのは、「長生きリスク」への備えが必須ということ。
払えなくなったときの備え
年金だけでは足りなくなり、毎月の管理費や修繕積立金を払うのが苦しくなることもあります。そんな時のために、前もって準備や工夫をしておくと安心です。
まず、毎月払っているお金の中に「実は使っていない保険」や「なくても困らないサービス」があれば見直しましょう。無駄を減らすことで、少しずつ支出を軽くできます。
また、生活の仕方を少し工夫することでも違いが出ます。例えば外食を減らして家で料理をする、電気をつけっぱなしにしない、といったことも積み重なると大きな節約になります。
それでも足りない時は「リバースモーゲージ」という制度を利用する方法もあります。
そして、どうしても難しい時には、子どもや親しい人に相談して一緒に解決方法を考えるのも大切です。「払えなくなったら終わり」ではなく、助けてもらえる道は必ずあると知っておくだけで、気持ちも楽になります。
💡 「老後資金が尽きる不安」そのものがストレス要因になります。選択肢を持っておくことが安心につながります。
老後に安心して暮らせるマンションを選ぶためのチェックリスト

老後は身体の変化や生活スタイルの変化が避けられません。だからこそ、今快適かどうかだけでなく、将来も安心して住み続けられるかを基準に考えることが大切です。
老後のマンション選びのポイント 📝
□エレベーターが複数基あり、停電時の対応も備えているか
⇒ 老後は足腰が弱くなるため、エレベーターは必須です。1基しかないと故障や点検の際に階段を使わざるを得なくなり、大きな負担になります。災害時には非常用電源で稼働するかどうかも確認しておきましょう。
□共用廊下や玄関が広めで、車椅子も通れるか
⇒ 通路が狭いと、将来介護が必要になった際に介助者と一緒に移動するのが難しくなります。見学時に実際に歩いてみて、すれ違える広さがあるかをチェックすると安心です。
□宅配ボックス・集会所など「外出が減っても暮らしやすい設備」があるか
⇒高齢になると重い荷物を持ち帰るのが大変になります。宅配ボックスがあれば、留守でも荷物を受け取れるので便利です。集会所は、住人同士が自然に交流できる場として、孤独を防ぐ役割も果たします。
□管理組合が定期的に総会を開き、修繕計画が透明化されているか
⇒管理組合がしっかり機能していないと、修繕が遅れたり積立金が不足して資産価値が下がるリスクがあります。議事録を見せてもらえるか確認することも大切です。
□徒歩10分圏内に病院・スーパー・公共交通があるか
⇒車を手放した後も暮らしやすいかは、この条件で決まります。特に病院は「かかりつけ医」だけでなく、夜間救急やリハビリ施設が近いと安心です。バス停や駅の距離も、通院や買い物の負担に直結します。
このように、選び方のポイントは「設備の有無」を見るだけでなく、将来の暮らし方を想像しながら確認することが大切です。
バリアフリー間取りのイメージ 🏠

- 廊下やトイレにL字型の手すりを設置
- 玄関から居室まで段差ゼロのフラット設計
- 引き戸中心で、体が弱っても片手で開閉可能
👉 小さな工夫が「自立した生活を長く続けられるか」を左右します。老後は自分がいつか動けなくなるかもしれない・・補助が必要になるかもしれないという未来を想定して住む場所を選ばなければ後で後悔する事態になりえます。
立地と生活環境の視点
Google Mapで実際にシミュレーションしてみると良いのが「買い物ルート」と「病院までの距離」。
例えば徒歩10分圏内にスーパーと内科があるだけで、老後の安心感はぐっと増します。

*画像はイメージです。このように、自宅から買い物ができるスーパー、病院が近くにあるマンションを積極的に選びましょう。いつまで車を運転できるかもわからないというリスクも考える必要があります。
老後向け「戸建て vs マンション比較」
| 項目 | マンション | 戸建て |
|---|---|---|
| 維持管理 | 管理組合が対応 | 自己負担・管理会社委託 |
| バリアフリー対応 | 新築・改修で整備済みが多い | リフォーム必須 |
| 防犯性 | オートロック・監視カメラあり | 自己対策が必要 |
| 交流 | 共用施設やイベントあり | 地域コミュニティ次第 |
- 維持管理の違いが安心感を左右する
◆マンション:管理組合が共用部分の清掃や修繕を担当するため、個人での負担は比較的少なく済みます。
◆戸建て:外壁塗装や屋根の修理などを自分で手配しなければならず、体力や判断力が衰える老後には負担になることがあります。 - バリアフリー対応は「最初から」か「後から」かの違い
◆マンション:新築時点でバリアフリー設計が施されている物件が多く、将来の介護にも対応しやすいです。
◆戸建て:段差解消やトイレ拡張などの工事が必要になることが多く、追加費用と工期を考慮する必要があります。 - 防犯面ではマンションが有利
◆マンション:オートロックや監視カメラ、管理人の存在によって、不審者が侵入しにくい仕組みがあります。
◆戸建て:立地や防犯意識によって安全性に差が出やすいため、自分で防犯設備を整える必要があります。 - 交流機会の質の違い
◆マンション:集会所や管理組合の活動を通じて、同世代や近隣住民と交流する機会が自然に生まれます。
◆戸建て:地域の町内会やご近所づきあい次第で孤立しやすく、住む場所によって差が大きいのが特徴です。
まとめると、「管理や安心を重視するならマンション」「自由度や庭を楽しみたいなら戸建て」という住まい方のスタイルによる違いが大きいといえます。
👉 より詳細な費用比較は「戸建てとマンションどっちが正解?30年総額で見ると?」をご覧ください。
価値が下がらない老後向けマンションの選び方と資産価値チェック

「子どもに残したい」「将来売却して老人ホームの資金にしたい」——そんな希望を持つ方にとって、マンションの資産価値を守れるかどうかは非常に重要です。実は同じ築年数の物件でも、数百万円以上の差がつくことがあります。
資産価値チェックリスト ✅
- 駅から徒歩10分以内か?
- 大規模修繕の履歴と計画があるか?
- 管理組合の健全性(修繕積立金残高・滞納率など)
- 周辺エリアの将来性(再開発計画や人口動態)
価格下落のイメージ 📉
築年数 平均価格下落率
10年 ▲10〜15%
20年 ▲30%
30年 ▲40〜50%
👉 ただし「駅徒歩5分以内」「人気学区」「大規模修繕実績あり」など条件が揃えば、築30年でも価格を維持するケースがあります。
リセールバリュー(将来売却時の価値)の高い物件の共通点と確認方法
- 大規模マンションで管理コストが安定
→ 管理費・修繕積立金の「1戸あたり負担額」が低いかどうかを販売資料で確認できます。 - 商業施設や医療機関が徒歩圏内
→ Google Mapで実際の距離を調べ、雨の日や荷物を持った時に歩けるかをイメージしておくと安心です。 - 管理人常駐やコンシェルジュ付き
→ 内覧時に管理人室を確認し、勤務時間や対応内容を聞いてみましょう。 - 修繕履歴や長期修繕計画が公開されている
→ 管理組合の議事録や長期修繕計画を取り寄せ、外壁や配管の修繕実績があるかを必ず確認してください。
👉 ポイントは、「資料で確認」+「現地で聞く」の両方を行うこと。表面だけで判断せず、具体的に裏付けを取ることが失敗を防ぎます。
資産価値を失ったマンションの実例
👉 こうしたリスクを避けるには、購入前に「長期修繕計画」や「総会議事録」を必ず確認しましょう。
専門家の視点を取り入れる
「自分に合う物件はどれか?」「将来も資産を守れるのか?」を判断するのは、初めての購入者には難しいものです。そんなときは専門家の目線を借りることが、失敗しない一番の近道です。
不動産鑑定士やFPは立地・築年数・管理履歴を総合的に見て判断します。

さらに私たち設計事務所+工務店の視点から言えば、自然素材や耐久性に優れた設計は将来的なリフォーム費用を抑え、資産価値を落としにくくします。
👉 神奈川で老後の住まい選びに悩んでいる方は、私たちあすなろ建築工房にぜひご相談ください。設計と施工の両面から、費用面・暮らしやすさ・資産価値まで含めて最適なプランをご提案します。
お気軽にこちらからどうぞ → 無料相談はこちら
まとめ:老後マンション選びで後悔しないために
- 費用面:管理費や修繕積立金は上昇する前提で計画を立てる
- 住みやすさ:バリアフリー・立地・管理体制を重視する
- 資産価値:駅近・管理良好・修繕履歴を必ず確認する
老後の住まいは「今の便利さ」だけでなく「20年後の安心」まで見据えることが大切です。
神奈川で老後の住まいを検討している方は、私たちあすなろ建築工房がサポートいたします。
👉 問い合わせ・メルマガでの情報提供をご所望の方はこちら
他の記事をみる