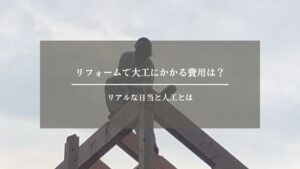【空き家問題】将来空き家にならないための家づくりとは?
近年、空き家の数は年々増加しています。
総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数はこの20年で約1.5倍に増え、今や850万戸を超える規模にのぼります。
こう聞くと「うちは関係ない」と思われるかもしれませんが、これは“これから家を建てる人”にも決して無関係な問題ではありません。
むしろ、「どのような家を建てるか」「どんな暮らし方をするか」が、将来の空き家化を防ぐ鍵となります。
今回は、これから住まいを建てようと考えている皆様に向けて、
「将来空き家にならないための家づくり」に必要な視点をご紹介します。
空き家問題|増えているのは、なぜ?

日本の家が空き家になる大きな理由は、「世代を超えて住み継がれていないから」です。
かつては「親の家を引き継ぐ」のが当たり前だった時代もありましたが、現代では以下のような理由で空き家になるケースが多く見られます。
- 高齢の親が施設入居後、自宅が10年以上放置されてしまう
- 相続後、「いつか住むかも」と気持ちの整理がつかず手をつけられない
- 解体費やリフォーム費が高額で、活用や処分が難しい
- そもそも家自体が現代の生活様式に合っておらず住みにくい
空き家が放置されると、傷みが急速に進み、いずれ誰も住めない状態になってしまいます。
つまり、“空き家は勝手にできる”のではなく、「適切に残されなかった家」が、空き家になってしまうのです。
1|30年後も選ばれる性能と設計を考える
これから家を建てるなら、最初から「将来も価値が残る家かどうか」を意識することが重要です。
見た目の美しさだけでなく、「断熱性」「耐震性」「維持のしやすさ」など、長く快適に暮らせる性能こそが、住宅の資産価値を左右します。
特に、極端な狭小地や3階建ての住宅は、将来の高齢化や相続時に住み替えづらくなることがあります。
どんな人でも暮らしやすい“普遍的な設計”は、将来的にも選ばれやすい家につながります。
“安く建てる”よりも、“価値を長く保てる家を建てる”という視点が、空き家にならない家の第一歩です。
2|住み続けやすいだけでなく、住み替えられる家を
「家は一生住むもの」と思われがちですが、実は“住み替えること”を前提にした家づくりこそ、これからの時代に合ったスタイルです。
たとえば、お子さんが独立された後、ご夫婦2人だけで暮らすには家が大きすぎると感じる方も少なくありません。また、ご自身の将来の介護や生活スタイルの変化を見越して、売却・賃貸・相続がしやすい家にしておくことで、住宅の資産価値を保ちやすくなります。
住み替えがしやすい家には、次のような特徴があります。
- 普遍的な間取りや構造(リフォームしやすい)
- 耐震・断熱などの基本性能が確保されている
- 立地や環境に魅力がある
- メンテナンス履歴が残されている
家は「建てた人のため」だけでなく、「次に住む人にもやさしい家」であることが大切です。
3|メンテナンス性を考慮した“手入れのしやすい家”を
家は「手入れをしてこそ長持ちする」ものです。
いくら高性能な素材を使っていても、定期的にメンテナンスがされなければ性能は徐々に低下します。
空き家になってしまう家の多くは、「手がつけられないほど劣化してしまっている」状態です。
例えば…
| 雨漏りによる構造腐食 給排水管の破損 カビやシロアリの被害 こうした事態は、定期的な点検と補修で防げるものばかりです。 |
家を建てる段階で、「将来手入れがしやすい設計」や「修繕がしやすい素材」を選ぶことは、
自分たちが住んでいる間の快適さだけでなく、家を残すうえでも非常に重要な視点です。
4|「解体費」も将来のコストに含めて考えておく
最近では、30坪ほどの家を解体するのに300万円以上かかることもあります。
地域によっては、土地価格よりも解体費のほうが高くなるケースもあり、これが“放置される空き家”の原因になっています。
だからこそ、「解体しやすい構造」や「将来の処分コストを意識した設計」も、現代の家づくりには必要です。
もちろん、住み続けることを前提にした家ではありますが、万が一の出口戦略として「どう終わらせるか」まで想定しておくと、家の価値と管理しやすさはぐっと高まります。
5|子どもや地域に負担を残さない家をつくるという視点
将来、自分たちが高齢になったとき。
この家をどう残すか、どう引き継ぐかを考えることは、自分自身だけでなく、子どもや地域への思いやりにもつながります。
使われない家は朽ちていき、周囲にも悪影響を及ぼすことがあります。
一方で、性能が高く、しっかりメンテナンスされた家は、次世代に資産として受け継がれる可能性を持ちます。
空き家問題は、誰かの問題ではありません。
私たち一人ひとりが「残せる家」「続けられる暮らし」を選ぶことが、未来への備えになります。
まとめ|“空き家にならない家”は「建て方」で決まる
空き家問題は、行政や社会だけが解決するものではありません。
一棟一棟の家づくりの選択が、地域の未来を左右します。
- 30年後も価値が続く高性能な家
- 世代を超えて住み継がれる設計
- 手入れがしやすく、活用しやすい住宅
これらを意識して家を建てることが、空き家にならない家づくりの第一歩です。
あすなろ建築工房では、目の前の暮らしだけでなく、未来に責任を持てる家づくりをご提案しています。「価値の続く家にしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
他の記事をみる